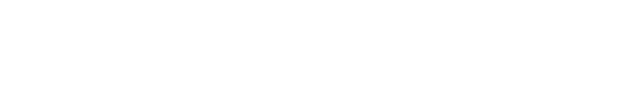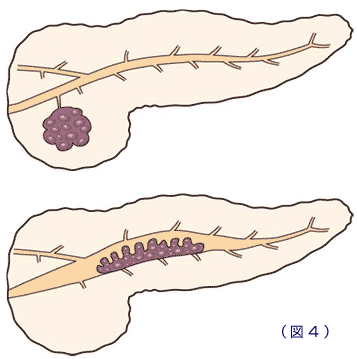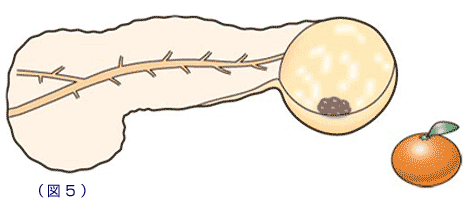膵臓の疾患について
膵臓癌(通常型膵癌)
1.症状
膵癌に特有の症状はなく、早期の発見が困難な疾患です.糖尿病の突然の悪化や腹痛(膵炎)は、膵癌を考える必要があります。最も大切なことは膵癌を疑うことであり、専門病院で適切な検査を行うことにより、早期の発見が可能な場合があります。腫瘍のできた場所によって症状は異なりますが、病気の進行にともなって黄疸、腹痛、背部痛などが出現します。
2.診断
膵癌の進行度(ステージ、=進み具合)を正確に診断することは、適切な治療を行う上での第1歩です。正確な診断のために、MD-CT, MRI (MRCP), PET-CT, ERCP, EUSなどの最新検査技術を積極的に取り入れています。
3.治療
膵癌の治療は単一の治療法だけでは不十分であり、手術(外科的切除)、放射線療法、化学療法、集学的治療、チーム医療などが大切と考えられています。
- 手術(外科的切除)
手術は根治の可能性がある唯一の治療法です。わが国で行われた「Stage IVa膵癌を対象とした手術vs.化学放射線療法のランダム化比較試験」では、手術の化学放射線療法に対する優位性が証明されています。当科では1981-2008年に300例の膵癌手術症例(膵切除は約700例)を経験しており、このうち80%に肉眼的根治術を施行しました。この中には血管合併切除ー門脈合併切除140例(47%)、動脈合併切除37例(12%)ーが含まれています。膵切除とともに血管切除を行うことにより治癒手術が可能と判断される場合には、積極的に血管合併切除を行っています。これまでの経験から、治癒切除率のみでなく手術の安全性も向上しています。具体的な手術術式については、4)膵臓癌に対する手術術式を参照。 - 放射線療法
放射線治療は、局所(放射線がかかった部位)に対する治療の効果があり、これまでは切除不能な局所進行症例に対して施行されてきました。現在当科では、治療成績を向上させる目的で、手術と組み合わせた治療に取り組んでいます.すなわち、手術前に放射線照射(±化学療法)を行った後に手術を行う、術前放射線療法または術前化学放射線療法を行っています。使用する放射線としては、従来のエックス線、ガンマ線に加えて、重粒子線(炭素イオン線、放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院との共同治療)を用いた治療を行っています。 - 化学療法(抗癌剤)
化学療法は前2者と異なり全身的な治療効果が期待でき、膵癌の治療成績を改善するためには不可欠な治療法であると考えられています。保険適応となっている薬剤(ジェムザール、ティーエスワンなど)を中心に治療を行っていますが、臨床研究として新規抗癌剤による治療も行っています。切除不能例に対する化学療法、手術後の補助化学療法のほか、臨床研究として術前投与(NAC)などの取り組みも行っています。 - 集学的治療
膵癌の治療成績の改善には、手術、放射線療法、化学療法などの利点をうまく組み合わせた集学的治療が大切であり、その意義が近年明らかになってきています。 - チーム医療
膵癌治療には、チーム医療が必要であると考えています。肝胆膵外科チームは消化器内科医、放射線科医、腫瘍内科医、看護師、薬剤師、緩和ケアチーム、ソーシャルワーカーと綿密な連携をとり、チーム医療を心がけています。 また、画一的な標準治療のみを行うのではなく、患者さんと十分に話し合い、ひとりひとりに最も適したな治療を行うことを常に心がけています。
4.手術術式
膵臓癌の手術は、腫瘍のできた場所によって手術の方法が異なります。膵頭部の癌では膵頭十二指腸切除術、膵体尾部の癌では膵体尾部切除術、膵全体の癌では膵全摘術が施行されます。
- 膵頭十二指腸切除術(PD, SSPPD, PPPD)
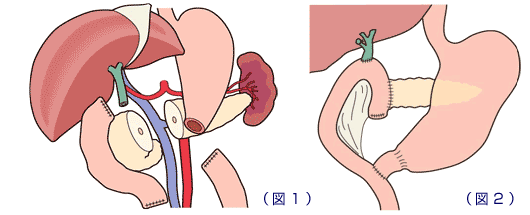 膵頭部、十二指腸(±胃)、胆嚢および胆管を摘出する手術です(図1)。膵頭部周囲のリンパ節や神経なども摘出します。癌が門脈に浸潤している場合には門脈を合併切除再建します。切除後には、膵臓と空腸、胆管と空腸、胃(十二指腸)と空腸を吻合して膵液、胆汁、食事の通る経路を再建します(図2)。
膵頭部、十二指腸(±胃)、胆嚢および胆管を摘出する手術です(図1)。膵頭部周囲のリンパ節や神経なども摘出します。癌が門脈に浸潤している場合には門脈を合併切除再建します。切除後には、膵臓と空腸、胆管と空腸、胃(十二指腸)と空腸を吻合して膵液、胆汁、食事の通る経路を再建します(図2)。 - 膵体尾部切除術(DP)
膵体尾部と脾臓、膵周囲のリンパ節や神経を摘出する手術です.大腸、副腎、門脈、腹腔動脈などに癌の浸潤を認める場合には、これらの臓器・血管を切除します(図3)。
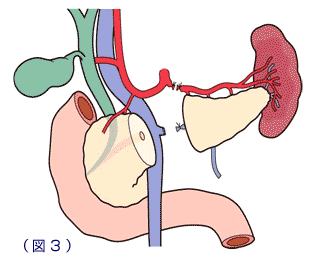
- 膵全摘術(TP)
膵臓を全て摘出する手術です.十二指腸(胃)、胆管・胆嚢、脾臓も一緒に摘出します。膵全摘後には、胆管と空腸、十二指腸(胃)と空腸を吻合します。膵全摘後にはインシュリンの投与や消化酵素剤が必要になりますが、手術後の生活の質(QOL)は以前と比較すると、格段に良好となっています。
膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は、膵管から発生し、腫瘍細胞が粘液を多く産生することにより種々の膵管拡張を来す疾患です。分枝膵管(細い膵管)から発生する分枝型、主膵管(太い膵管)から発生する主膵管型、および混合型に分類されます(図4)。この腫瘍は、発生初期には良性ですが、進展に伴って悪性化(癌化)することが知られています(malignant potential)。従って、適切な時期に治療(手術)を行うことが重要な疾患です。早期で良性の可能性が高い場合には、すぐに手術を行わずに経過観察をし、悪性の可能性が高い場合や腫瘍による症状がある場合には手術を行います(手術術式は膵癌の手術術式を参照)。
膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)
膵粘液性嚢胞腫瘍は、中年女性の膵体尾部に好発します(図5).IPMNと同様にmalignant potentialを有する腫瘍であるため、適切な時期に手術を行うことにより治癒が見込める疾患です。
膵内分泌腫瘍(PNET)
膵ランゲルハンス島細胞由来の腫瘍を膵内分泌腫瘍または膵島細胞腫瘍といいます.ホルモンを産生するものを機能性膵内分泌腫瘍、産生しないものを非機能性膵内分泌腫瘍と分類します.治療は切除が原則です。
Solid pseudopapillary tumor (SPT)
若い女性に好発します.基本的には良性ですが、悪性例もあり、肝転移やリンパ節転移を認める場合もあります.治療は切除が原則です。
膵漿液性嚢胞腫瘍
ほとんどが良性腫瘍であり、多くの場合は経過観察となります。症状をともなう場合や、悪性が疑われる場合は切除を行います。
急性膵炎(感染性膵壊死)
急性膵炎は腫瘍ではありませんが、外科的治療が必要になることがあります。急性膵炎はアルコール多飲や胆管結石などが原因で起こる膵臓の急性炎症です。軽症のものは膵臓のみで炎症が治まりますが、重症になるにつれて全身性炎症反応症候群 (SIRS)へと進展し、重症急性膵炎ではしばしば臓器不全症状を来たし生命の危機を招きます。 重症急性膵炎の中でも膵臓の一部が壊死してしまう壊死性膵炎は非常に重篤であり、さらに壊死部に感染を合併した感染性膵壊死は死亡率の高い重篤な疾患です。これらの患者さんはICUにおける集中治療に加えて、壊死部を除去する手術(ネクロセクトミーおよびドレナージ)を行うことがあります。現在では開腹手術は最終手段として用いられており、経皮的治療、内視鏡的治療が先行して行われています。
慢性膵炎
慢性膵炎は腫瘍ではありませんが、外科的治療が必要になることがあります。慢性膵炎は急性膵炎を反復した結果、膵組織が繊維化し、膵臓の機能低下を来す疾患です。重度になると膵機能が廃絶してしまい、糖尿病や消化不良が起こります。慢性炎症が続くと膵管の破綻を来たし、膵性疼痛(非常に頑固な持続する痛み)や仮性嚢胞を合併したり、門脈閉塞による門脈圧亢進症(消化管出血の原因となる)を合併します。これらに対しては、膵管の破綻形式に基づいて、内視鏡的治療、経皮的治療、手術が行われます。急性膵炎と同様にアルコール多飲が原因であることが多く、身体治療に加え、禁酒指導や社会復帰支援などの精神的・社会的治療も併せて行っています。
*図表はすべて、MEDICAL VIEW社刊「インフォームドコンセントTool 消化器外科イラストLIBRARY」から引用改変しました。